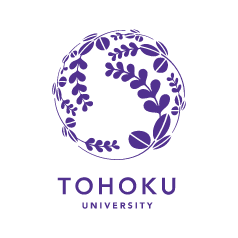幅広く学んで視野を広げる-検察官の道を選んだ法曹として

池上 政幸
2014年10月最高裁判所判事就任、2021年8月定年退官。
1951年宮城県仙台市に出生。宮城県仙台第一高校出身、1975年東北大学法学部卒業。
司法修習(29期)後、検事任官。東京地検、水戸地検、仙台地検、釧路地検を経て、法務省刑事局刑事課長、総務課長、官房長などを歴任。その後、最高検察庁公判部長、刑事部長、次長検事、名古屋高等検察庁検事長、大阪高等検察庁検事長を経て、最高裁判所判事に任命される。
身近にいた東北大学生に影響されて
私は、仙台で生まれて、小学生のころ3年間ほど父の仕事の関係で福島県にいたことを除けば、ずっと仙台で育ちました。仙台は「学都」といわれていて、東北大生を非常に尊敬している町でした。
また、当時の住まいの近くに東北大の学生寮がありました。そこで、児童会の合唱とか演劇とかの指導してもらったり、寮の部屋に遊びに行ったりと、学生さんと交流がありました。彼らの部屋は難しそうな本がたくさんあるし、英語の歌が流れていてかっこいいなと思ったことを覚えています。
大学生というのは非常に真面目で、自由に勉強をしていてすごいなと思っていました。そういう中で知らず知らずのうちに、東北大はすごい大学だ、将来入れたらいいなと思うようになってきたのだと思います。

東北大学学生寮寮祭仮装行列(1960年11月:東北大学関係写真データベースより)
生徒会の活動の中で法解釈の面白さを垣間見る
法学部を目指すきっかけについていえば、仙台に高等裁判所が所在していることもあって、裁判の報道も多く、なんとなく裁判というものに興味を抱いていたということはあったと思います。
中学生時代は、1年生から軟式庭球部、2年生の秋ごろから応援団の幹部、学校新聞の編集委員長というように、課外活動に情熱を燃やしていましたね。そんな中、3年生の夏に出場したソフトテニスの大会で非常に悔しい敗退をしたのです。その悔しさをきっかけに、次は生徒会活動を真面目にやってみようという気持ちになったのです。3年生の夏ということで、受験勉強を始めなければいけないのに。(笑)
そこから半年間、生徒会長をやりました。生徒会といえば、会則とか様々な規程があります。ところが指導される先生との間でも、会則等の条文の解釈について違いがあるのです。また、何の問題だったか、会則の改正等をやりましたが、条文をどのように表現するか、解釈はどう考えるかという議論が結構面白いなと思ったのです。もちろんこれは法解釈とは 違いますが、法学部を目指す一つのきっかけになったのではないかなと思っています。
文武両道の高校生時代――教養講演で法律への興味が刺激される
昭和42年(1967年)の4月に、宮城県仙台第一高等学校に進学しました。県内1,2を争う進学校でしたが「文武両道」を掲げていました。私は、中学時代と同様に軟式庭球部に入ることにしました。

宮城県高校総体軟式庭球団体戦優勝時の記念写真(1969年5月:優勝旗の左斜め後ろが池上さん)

現在の仙台一高軟式庭球部 (写真提供:仙台一高)
入学後間もない6月に、教養講演として、最高裁判事を退職されてから数年程経ったという先輩のお話を聞きました。講演終了後の質疑応答の中で、上級生の一人が「最高裁は統治行為論を採って日米安保条約の合憲性を判断しないで逃げているけれど、裁判所としての役割放棄ではないのか」などという質問をしたのです。それに対して、講師からは「裁判所は国会と違って主権者たる国民から、直接そのような政治的な問題、とりわけ他国と安全保障条約を結ぶという高度な政治問題の合憲性判断をすることについて、裁判所は主権者たる国民から負託を受けていない。私はそれが三権分立の下における司法権の限界だと思っている。」という趣旨を答えていました。よく理解できたわけでもなく、すぐに腑に落ちたわけでもないのですが、今まで気づかなかったことに目を向けるきっかけになりました。裁判官という仕事は難しいけどやりがいのある仕事のようだなという感覚を抱きました。
その後、軟式庭球部で練習に励みつつ高校生活を送りましたが、2年生の冬、理系文系のクラス分けの希望を出さなければならない時期になりました。色々と考えた末、文科系への進級を希望することにしました。そして、志望学部は法学部を選ぶことに決めました。
当時、読んだ進学雑誌には、法学部卒業生の進路として、裁判官・検察官・弁護士についての記載がありました。弁護士というのは、独立した自由業で、法律を駆使して依頼者の権利を守り、社会正義の実現に繋がる仕事だと書いてあり、これはやりがいのある職業のようだと思いました。裁判官については、法廷での審理に基づいて判決を下す人だということは分かりましたが、なんとなく堅そうな仕事だと感じましたし、検察官については、警察官の仕事との違いもよく分からず(笑)、具体的なイメージはまったくつかめませんでした。
校訓 (写真提供:仙台一高)
他方で、法学部で学んだ知識は、企業に入ったり公務員になったりした場合にも役に立つということも書いてあり、大学卒業後の職業選択にも多様な選択肢があるということも書かれていました。
そのような漠然としたイメージで法学部を志望することにしたのです。
そんな中で、当時の情勢として、東京大学の紛争が激しくなり、2年生の終り頃には安田講堂事件が起きて、その年の東大の入試が中止になったのです。その影響でその年の東北大の入試のレベルもかなり上がってしまって。翌年の東北大の入試に合格できるかなと不安な気持ちになりました。しかし、3年生の夏まで部活動を頑張り、秋から本格的に受験勉強をして、なんとか翌年4月に東北大学法学部に入学することができました。

川内・教養部封鎖解除(1969年11月:東北大学関係写真データベースより)
東北大学法学部の学生時代と司法試験
入学すると、まず川内にあった教養部で、一般教育科目や外国語科目を必修として履修することになっていました。そして、教養部を終えると、専門課程としての法学部に進学し片平にあった法文教室等で学ぶものとされていました。
法学部(専門課程)では、必修科目はなく、卒業論文等も存在せず、演習科目(ゼミ)を履修するかどうかも自由で、合計90単位を修得すれば卒業できることになっていました。さらに、文学部・経済学部の科目を履修することができ、20単位まで卒業単位に含めることができるとされていたのです。入学して間もなく、長い伝統をもつこの自由選択制を知ったとき、東北大学法学部では、学生の自主性を重んじ、法学・政治学という専門科目だけではなく、人文・社会科学の幅広い分野を学べることが期待されているのだなと感じました。
私は、大学でも学友会の軟式庭球部に入って、4年生の夏の七帝戦まで活動を続けることにしていました。その一方で、入学後間もなく、いずれ司法試験を受けたいという気持ちが芽生えてきました。
教養部では、それなりに幅広く履修していたつもりですが、2年次の6月頃から、学生紛争の影響で教養部の講義等が閉鎖されたたりしたため、英語・ドイツ語の外国語科目や法学講読(英独の文献の講読)科目を十分に履修することができませんでした。もっとも、自習すればよかったのですが、講義がないと友人達と喫茶店等に行って雑談に花を咲かせたり、早めにテニスコートに行ったりしていたので自業自得かもしれませんが(笑)。
片平の法文教室での専門科目の講義は、極めてレベルの高いものでした。とりわけ、2年次には、木曜日(終日)と土曜日の午前に、憲法・民法(総則・物権法)・刑法(総論)などの講義を聴くことができたのですが、その専門性の高さと難しさには強い印象を受けました。小嶋和司教授は、憲法学を政治論ではなく法律学として構築するとして、最高裁判例に法源性を認めるという立場からの講義でしたし、鈴木禄弥教授の講義は、「なし崩し的物権変動論」をはじめ判例・通説の解釈論とは異なる理論を説かれていました。荘子邦雄教授の講義も、その犯罪論体系は初学者には難解なものでした。これは、相当気合いを入れて学ばなければついていけないと感じました。また、3年次、4年次に学んだ法律科目は、それにもまして、難しく専門性の高いものでした。
ただ、運動部の厳しい練習の合間に、静かな雰囲気の講義を聴きノートを取っていると、講義内容が非常に深遠なものに感じられて、結構頭に入って来るようになりました。また、時には、教授の講義が知的刺激に満ちていて楽しいという気持ちになることもありました。もっとも、軟庭部のシーズン中には予習復習をしないまま聴講することも多く、よく理解することができないままに終わることが多かったのですけれども(笑)。

片平・法文1号館正面玄関(1972年:東北大学関係写真データベースより)
演習科目(ゼミ)についていうと、3年次には荘子教授の「刑法ゼミ」に参加を許されました。最高裁判例等を素材として問題点を議論するゼミでしたが、4年生が過半数であり、既に司法試験の受験準備を進めていた先輩が多く、荘子教授や岡本勝助手(当時:現在は東北大学名誉教授)と4年生とのやりとりにはとてもついて行くことができず困惑するばかりでした。しかし、ゼミの後の飲み会や年度末の作並への旅行会は楽しい思い出です。
4年次には、菅原菊志教授の「商法ゼミ」に加わり、英国貴族院(後の最高裁判所)の会社法に関する判例を評釈した文献の講読をしました。同級生だけのゼミだったので、ゼミ後のコンパは楽しく盛り上がり、菅原教授からも楽しくお話を聞くことができました。
また、小田滋教授の「国際法ゼミ」にも加わりました。法典化の動きが始まっていた海洋法についての文献を講読するゼミでした。当時、小田教授は、国際会議や国際裁判に係わっておられご多忙の中でしたが、最新の「海の国際法」の知識を教えて頂きました。
また、実定法の専門科目以外にも、法学部では、政治学史、法理学、比較外国憲法等を、文学部では社会学等を学びました。いずれも視野を大きく広げてくれる科目でした。
司法試験受験の決意をしつつ、4年生の夏の大会を終えたら秋から本格的な受験勉強に取り組もうと考えており、実際に4年次の秋になると川内の図書館にこもり受験勉強を始めました。そして、何とか両親の了解を得て、2単位を残して卒業せず留年することにしました。この川内の図書館や川内に移転してきた講義等などの学習環境を変えたくなかったからです。
受験には相当の期間がかかると覚悟していましたが、幸運が重なったためか、翌年9月には司法試験に合格することができました。

六法を開き、条文に向き合う姿はまさに裁判官
検察官への道を選ぶ
私が検察官を志望するようになったきっかけを思い出してみますと、まず、当時、教養部で同じクラスだった蒲原正義君(元カザフスタン駐箚特命全権大使)から2年次の夏前の頃に「うちの親父は検事で今度東京に帰って来たんだが、司法試験を志望しているなら会って検事の話を聞いてみないか」と言われたことがあります。
彼の御父上は、鳥取地検検事正から最高検に戻ってこられたところであり、東京の官舎で、色々とお話を伺いました。御父上からは「検事というのは、警察から送られてきた事件でも、改めて記録を検討し、さらに必要な証拠を集め、事件全般をよく知った上で、起訴・4不起訴の判断をし、公判では、証拠に基づいて被告人に適正な判決を求めるという実に能動的な仕事だよ」などと話していただきました。このときに、初めて、検察官についてのイメージを知ることができました。
また、刑法ゼミの荘子教授は、検事にお知り合いも多く、酒の入った席では、よく「検事はいい仕事だぞ」などと仰っていました。そして、4年生だった先輩の一人が検事志望で、翌年、司法試験に合格していきました。また、同級生の一人も検事の道を目指していました。そんなゼミの雰囲気が私を検事志望にさせる一因となりました。その後、翌年の荘子ゼミからも検事の道を選んだ方がいます。
そして、司法修習生の2年目の検察実務修習では、指導担当検事の下で被疑者・参考人の取調べを担当し、起訴状、不起訴裁定書、公判における冒頭陳述・論告等を起案し、法廷でも公判担当検事の隣に座り傍聴するなどの検察官の実務を学びました。検察官は、受け身の仕事ではなく、実に能動的な仕事だと感じました。不偏不党の立場から厳正公平に実体的真実を追及するという姿勢にも惹かれました。
また、指導官からは、検察官になると、最初の5年から10年ぐらいは各地の検察庁で捜査と公判の実務を担当するけれども、その後は、希望や適性に応じて、法務省をはじめてとする行政機関、在外公館、司法研修所や法務総合研修所の教官・研究官など多様な職を経験して視野を広げる機会も設けられているなどということも教えられました。
こうした修習に加え、司法研修所の検察教官や実務修習での指導官の人柄にも惹かれたこともあって、私は修習2年目の秋には、最終的に検察官希望を確定させたのでした。
多様な職務を経て視野を広げる
私は、昭和52年(1977年)4月、東京地方検察庁検事に任命されました。そして、検察官任命後9年間は、東京、水戸、仙台の各地検で捜査と公判の実務を担当したのです。事件も多く多忙でしたし、起訴・不起訴の処分や公判での主張立証方法の策定などについて悩むことも多かったのですが、検察庁では検察官同士で事件の問題点を相談し合う雰囲気があり、先輩や同僚の検察官には色々と相談して助けてもらいました。
昭和61年(1986年)3月、私は、法務省刑事局付を命じられ、刑事課で一般刑事事件に係る事務を担当することになりました。他省庁の課長補佐のような仕事です。全国の検察庁からの事件の報告を取りまとめ、所管する事件について国会で質問があるということになると、法務大臣や刑事局長の答弁案を起案しました。それぞれの立場によって、刑事事件についての見方が違うということを学びました。また、全国の検察庁の会議があると、大臣訓示や局長指示の原案を作成することもありました。検察庁が法令の解釈や検察権行使の方針といった面では、検察官一体の原則として、統一的に運用される必要があるという側面も理解できるようになりました。
さらに、翌年11月には、法務大臣秘書官事務取扱を命じられました。法務省では、他の各省と同様、法律上、大臣秘書官1名が置かれていますが、政治的任用の特別職であり、多くの場合、大臣の就任時にそれまでの議員としての公設秘書の方が任命されていました。大臣秘書官は、一般に、大臣の政治家としての仕事(政務)を補佐されることが多いので、その代わりに、中堅の検事に、大臣秘書官事務取扱(通称「事務秘書官」)を命じ、この事務秘書官が法務行政の事務的な面について大臣を補佐することになっていました。これまでとはまったく違う仕事でした。
私は、事務秘書官として、朝には大臣が登庁されるのをお迎えし、在庁している間はもとより、国会で質問を受ける際や記者会見をはじめとする対外的な発言をする際だけではなく、あらゆる場面で大臣が適切に対応することができるように、法務省各部局が作成した資料を鞄に入れて大臣が帰宅するまで、一日中随行して補佐する仕事をしていました。また、常時「ポケベル」を持って大臣と各部局との間で緊急に連絡を取り合う必要が生じる場合に備えていました。
法務省には、当時、大臣官房のほか、民事、刑事、矯正、保護、訟務、人権擁護、入国管理の7つの内部部局と外局としての公安調査庁がありました。法務省の行政は、「基本的人権の保全と法秩序の維持」という言葉で表現されるのですが、各部局の政策や業務には、かなり性質が違うものがあり、それぞれが独立性の高い行政でしたから、大臣との間で連絡調整する必要が生じることがまれではありませんでした。
おかげで、私は、法務省各部局の所掌事務やその政策等を学ぶことができました。また、ある大臣からは、「ことに臨んでは激せず躁(さわ)がず。冷静沈着に対処することが大事だ」ということも教えられました。このとき学んだことは、その後に法務・検察の仕事をしていく上で、大きな糧になったと思っています。
釧路地検北見・網走支部の勤務――その苦労とやりがい
その後1年程が経ってから、釧路地検北見・網走両支部の支部長を命じられました。オホーツク地方と呼ばれる地区で、両支部の面積は、静岡県とほぼ同じ広さでしたが、人口は12分の1の30万人くらいでした。両支部に検事は私一人で、副検事4名を含め職員は二十数名の規模でした。
支部長としての検事は、いわば「プレーイングマネージャー」で、自ら担当すべきと考えた事件は、検察官の一人として捜査・公判を担当し、その他の事件は、副検事等に配点して、捜査の結果を踏まえた起訴・不起訴の処分が適切なものかどうかなど決裁するという仕事をしていました。また、検察庁の行政事務の一端をも担当する仕事もありました。
北見から釧路地検の本庁まではJR線を乗り継いで4時間半ほどかかり、札幌高検までは、特急でもそれ以上かかったと記憶しています。インターネットもない時代には、どちらも大変遠い存在でした。そんな遠隔の地の北見・網走の両支部で、一人の検事あるいは一人の支部長として仕事をすることは、責任も重く苦労もありましたが、半面、やりがいも感じていました。また、北海道の小規模支部の視点から検察の組織をみるというのも得がたい経験でした。
北見・網走地方の厳しくも雄大な自然の中で、両支部の職員との楽しい交流も含めて思い出深い勤務となりました。1年10か月ほどの勤務で東京地検に異動となりました。
新しい司法試験の具体的イメージ作り――法務省人事課長時代
その後、法務省の大臣官房参事官として施設や国有財産の事務を担当し、次いで東京地検刑事部の副部長、法務省刑事局刑事課長、同総務課長の職を経て、平成13年(2001年)6月、官房人事課長を命じられました。
人事課の担当する事務の一つに、司法試験管理委員会(現在の司法試験委員会)の庶務担当として、(旧)司法試験を実施する事務がありました。当時、司法制度改革審議会の答申を受け、内閣に置かれた司法制度改革推進本部が、大学法学部、法科大学院の教育と有機的に連携した新しい司法試験を作り司法研修所における修習につなぐ新たな法曹養成制度を作り上げようとしていました。
そして、この有機的連携に関する法律ができ、司法試験法の一部改正も国会に提案されよることになっていたのですが、「点としての資格試験」ではなく法科大学院教育と有機的に連携した試験の制度とするといっても、具体的にどのような試験とするかについては必ずしも明らかではなく、その具体化を司法試験管理委員会の下で人事課が担当することになりました。
そこで、委員会の下に、大学の先生方や裁判官、検察官、弁護士を構成員とする「新司法試験の実施に係る調査研究会」が設けられ、その庶務も人事課が担当することになったのです。この研究調査会では、新たな司法試験はどうあるべきかという理念をはじめとして、各科目の試験時間、出題数、複数の科目にまたがる(いわゆる「大々問」)の出題の可否、問題の形式などについて、幅広く精力的な議論が行われました。この研究調査会の結論を踏まえ、新たにできた司法試験委員会の決定によって、具体的な新司法試験の具体的な実施方法が定められたのです。人事課の担当課付をはじめとする担当職員達が熱心にこの研究調査会の議論を支えてくれたことには今でも頭が下がる思いがします。こうした検討を経て、平成18年から新しい司法試験が実施されるようになりました。私は、その前に、松山地検検事正に異動となり、新司法試験の実施を担当者として見ることはできませんでした。
司法試験を含む法曹養成制度については、その後も何度か手直しが行われていますが、今後ともより良いものとなっていくよう願っています。
最高裁判事としての6年10か月
私は、その後、法務省の官房長、最高検の公判・刑事両部長、次長検事、名古屋・大阪両高検の検事長などを経て、平成26年(2014年)7月に職を辞しました。そして、その年の10月、最高裁判所判事に任命され、令和3年8月まで、およそ6年10か月間にわたり、その任にありました。本日、私に与えられたテーマは、検察官経験者としての話を中心にということでしたから、簡単に触れるだけにしたいと思います。
最高裁判事の仕事ぶりについては、東北大学名誉教授で元最高裁判事の藤田宙靖先生がその著書『最高裁回顧録――学者判事の7年半』にお書きになっているとおりであり、同窓の菅野博之最高裁判事も述べられていると思うので、重複を避けたいと思います。ただ、私も、平日は登庁すると、次から次と裁判官室に運び込まれる事件記録や資料と取り組む日々を送り、藤田先生が紹介している「席の冷める暇もない忙しさ」という言葉のとおりであることを実感しました。判断が難しい事件については、自宅で、休日も含めて深夜まで関係資料と取り組むことも稀なことではありませんでした。
最高裁は、最終的な司法判断を示す法律審ですから、小法廷に係属する事件の大部分を占める「持ち回り審議事件」であっても検討をおろそかにすることはできず、「審議事件」については、審議に備えて、関係する法令や判例・裁判例それに学説などを十分に検討して、小法廷の裁判官による審議の場では、法令の文理的解釈だけではなく具体的な事案の妥当な解決という観点からも適切な意見を述べ、論議を尽くすことが求められていました。大法廷に回付された事件は、憲法判断、判例変更などの重要な判断をするのですからなおさらでした。
この6年10か月余りの間に、私は、民事・行政事件で1万件余り、刑事事件で6500件余りの判断に加わりました。このうち、法律的判断を示した判例集・裁判集に登載されたのは、民事・行政・刑事をあわせておよそ170件(うち大法廷事件15件)でした。
老いて学べば死して朽ちず――新たな学び
最高裁判事を退官した後、縁あって東京・池袋にある古代オリエントの博物館のことを知りました。この博物館には。ハンムラビ法典のレプリカが展示してあるのですが、その「法典」の内容に興味を惹かれたのです。そして、この博物館の前館長で「法典」の原典訳などの著者の先生と知り合うこともできました。この先生のお話を聞き、著書等を読ませて頂くと、「社会あるところ法あり」という言葉のとおり、古バビロニア時代のこの「法典」には、民事的なものや刑事的なものを含め、学ぶべきものが多いように感じられました。そして、この法典だけではなく、これに先立つシュメールの法を含む古代メソポタミアの法文化に新たな興味がわいてきています。
「老いて学べば死して朽ちず」といいます。日本の法律家としての目で学び続けたいと思っています。

皇居や法務省も窓外に見える日本俱楽部にて
良い環境を活かして幅広い学びを
東北大学は、川内から青葉山にかけて自然豊かな広いキャンパスを持っていますし、法学部は昔から、ロースクールも含めて、優秀な教授や准教授の皆さんがたくさんいらっしゃいます。
90単位という自由な選択制の中で幅広く法学や政治学などを幅広く学んで、もし法律実務家を志望されるのであれば、視野が広く高い視点から物事を見られる法曹になって頂きたいなと思っています。
また、仙台は、旧制二高と東北帝国大学以来の伝統で、学生のみなさんや先生方を大切にして尊敬している町です。そのような学都仙台の良い学習環境の中で、力を伸ばしていっていただきたいと思っています。
聞き手:鈴木刀磨(4年)
藤田和郁見(3年)

(インタビューは2022年10月24日に行いました。)